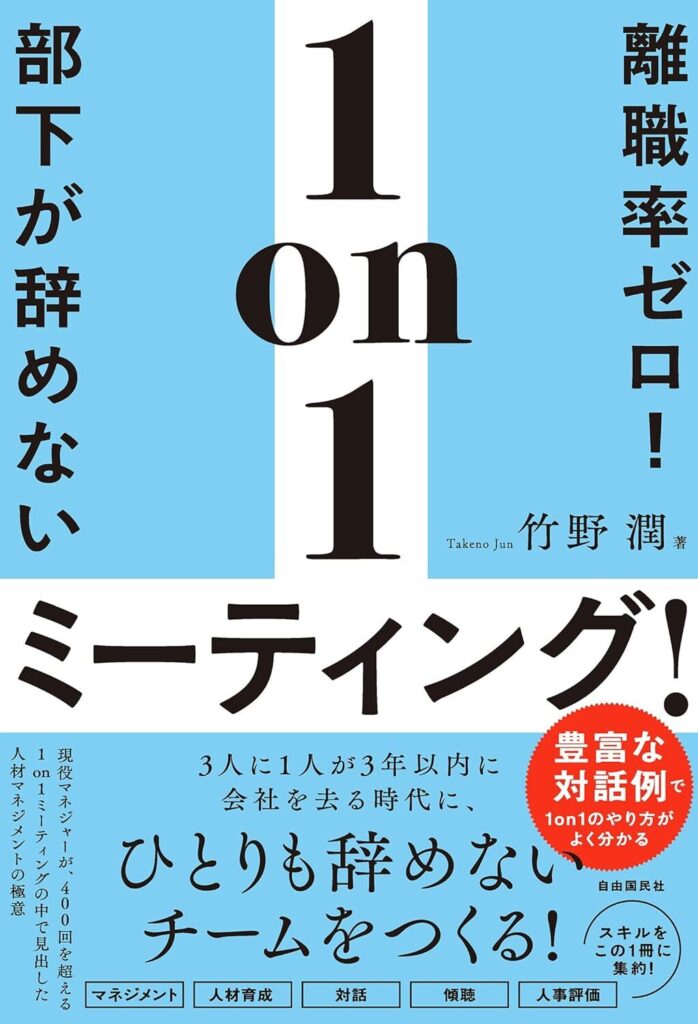
読もうと思ったきっかけ
仕事においてチームメンバーとのコミュニケーションを強化するために、毎週1回1on1を実施したことが仕事の成果に大きくつながっていると実感しています。
今年、7月にマネジャーへ昇進することとなり、1on1のレベルを上げたいと思い、読むことにしました。
本を読んだ感想
マネジャーの仕事は3つ
マネジャーの仕事は3つしかないと考えています。それは「マネジメント」「人材育成」「業績」です。それらはピラミッドの形をしていて、下から1階部分が「マネジメント」、2階部分が「人材育成」、3階部分が「業績」の順にのっかっています。 つまり、ピラミッドを支える土台部分である「マネジメント」が成り立たないと、2階の「人材育成」、3階の「業績」も成り立たないと考えて下さい。
マネジャーの仕事とはいったい何だろう。そんな疑問に答えてくれたのがこの本でした。
マネジャーの仕事は「マネジメント」「人材育成」「業績」であることはわかっていたのですが、構造を頭の中でイメージできていませんでした。ピラミッド構造になっていることがイメージできているかどうかが普段のマネジャー業務が変わってきました。
これまで私は「マネジメント」「人材育成」「業績」それぞれ個別に考え、それぞれ単独で考えて、業務を回してきていました。
しかし、そうではなく「マネジメント」は基本。
これは業務を回すというレベルではなく、できて当たり前。
チームメンバーの「人材育成」を行うことで、「業績」達成につながる。「業績」を達成ことと「人材育成」はつながっていて、それぞれ個別に考えるのではなく、連動している。
3つのことを意識すると難しいですが、それぞれつながっていると考えることで私はとてもスッキリし、マネジャーの仕事が腑に落ちました。
マネジャーが期中に必ず実施すべきこと
絶対に部下から文句が出ない評価のやり方は、「目線合わせ」と「フィードバック」
失敗談のエピソードには2つの教訓があります。
1つは「マネジャーの期待値を部下にはっきり伝えていなかった」ことです。みなさんの会社にも様々な役職があると思います。そして役職によって期待される役割・行動は異なります。
そして、もう1つは「期中でのフィードバックを実施していなかった」ことです。人事評価は、通常1年間の活動・成績に対して行われるものですが、1年は非常に長い期間です。部下は自分がイケているのか、イケていないのか、だいたいの感覚は認識できても、マネージャーが評価する自分の”現在地”をはっきりと認識することは困難です。そこで重要になってくるのが、部下の自己評価とマネジャーの評価の目線合わせです。
筆者の竹野さんが失敗談として部下が人事評価に納得がいかなかったことに対して書かれた教訓がこちらです。
私はまだマネジャーになり立てで人事評価の経験がありませんが、とても大事だなと思いました。自分自身の経験を思い出しても、私自身これまで部下として仕事をしてきましたが、評価が良かったときは納得できましたが、評価が悪かったときは納得できなかったことが多かったように思います。
そして、これまでたくさんの上司と一緒に仕事をしてきましたが、1つ目の「期待値を部下に伝えること」は実施されてきたことが多いですが、もう1つの「期中のフィードバック」はほとんどされた記憶がありませんでした。
気づいたら1年に1回の人事評価の時期になり、自分の評価が伝えられる。その時には結果を知るだけ。そこから結果を変えることはできないので、結局評価が悪かった場合は納得感も得られず、仕事に対するモチベーションが一定期間下がることになります。
自分自身の経験もそうだと感じたので、マネジャーとなった今自分自身が過去受けた同じことは部下にしたくないな、と思いました。
私は2週間に1回の頻度で1on1をしていますが、主に業務に関する相談などがメインでした。
この本を読んで、年初の目標設定時に部下と目線を合わせ、四半期に1度少なくとも半期に1度は期中のフィードバックをして、お互い納得感のある評価ができるようにしたいと思いました。
なお、この本では具体的に以下の内容も紹介されているので、具体的に知りたいと思われた方は購読をオススメいたします。
- どのように目線を合わせを行えばよいか(人事評価の目線合わせシートの活用)
- 目線合わせシートの部下、上司への活用方法
- マネジャーの期待値を提示するサンプルシート
マネジャーに求められる3つのスキル
「現代のマネジャーには、3つの要素が求められている」と私は考えています。
一つ目は「経済学」です。マネジャーは割り当てられたマーケットに対する最終責任者です。
二つ目は「心理学」です。成果主義やデジタル化が進展した現代においては、合理的なことが重要視される一方、人の感情や気持ちなどの目に見えない側面は、ないがしろにされがちです。部下は「正論」ではなく、「感情」で動く生き物です。
三つ目が「哲学」です。マネジャーには、マネジャーとしての世界観や基本的な考え方が備わっていなければなりません。「マネジャーは何のために存在しているか」、つまりマネジャーの”存在意識”を明確に言語化できなければいけません。
私がこれまでに思っていたマネジャーに求められるスキルとは「マネジメント」「リーダーシップ」「ビジョニング」といったスキルを想定していました。
でも、この本では私が考えていたスキルは、スキルというより仕事になるのだろうと感じました。仕事であれば繰り返し行えば習得できるようになると思っています。「マネジメント」「リーダーシップ」「ビジョニング」も初めは分からないかもしれませんが、何度も繰り返すことで自分なりのやり方が見つけられると信じています。
この本で書かれているスキルとは私のイメージでは、スキルというより「価値観」に近いそんな印象を受けました。
一人の人間としての「価値観」、マネジャーとしてというより一人の人間として魅力ある人になれるか、部下がこの人と一緒に働きたいと思える人になれるか、最後にマネジャーではなく、人として一番大事にすべきことを改めて教えていただいた気がします。
読んで得た気づき
私は書評では、どれだけたくさんの気づきがあってもまとめるのは3つだけと決めています。
そのため、この本で紹介したことはほんの一部にしかすぎません。例えば、以下のキーワードにピンときた方はご購読をオススメ致します。
- 1on1ミーティングを成功に導くために
- 1on1ミーティングに人事評価を導入する
- 部下タイプ別コミュニケーション術
この書評でこちらの本の良さを少しでも伝えることができていれば、とても嬉しく思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



コメント